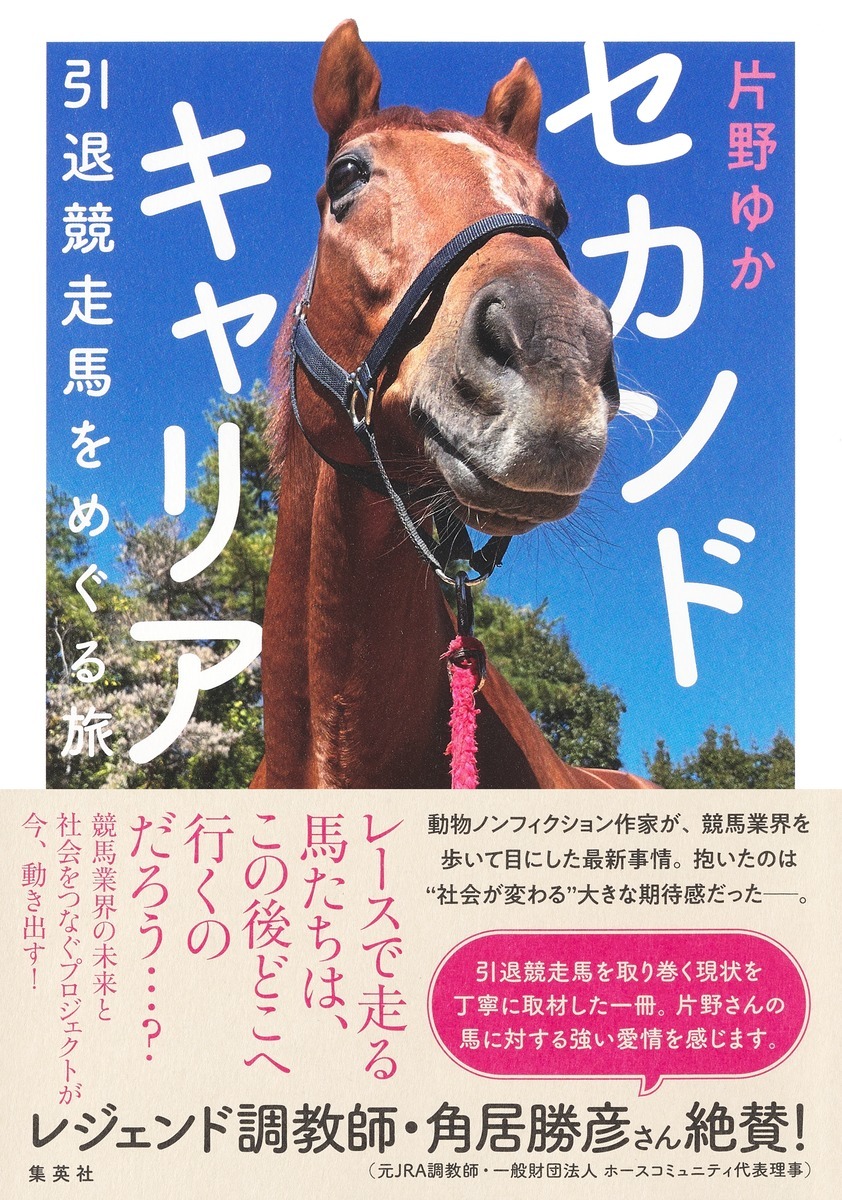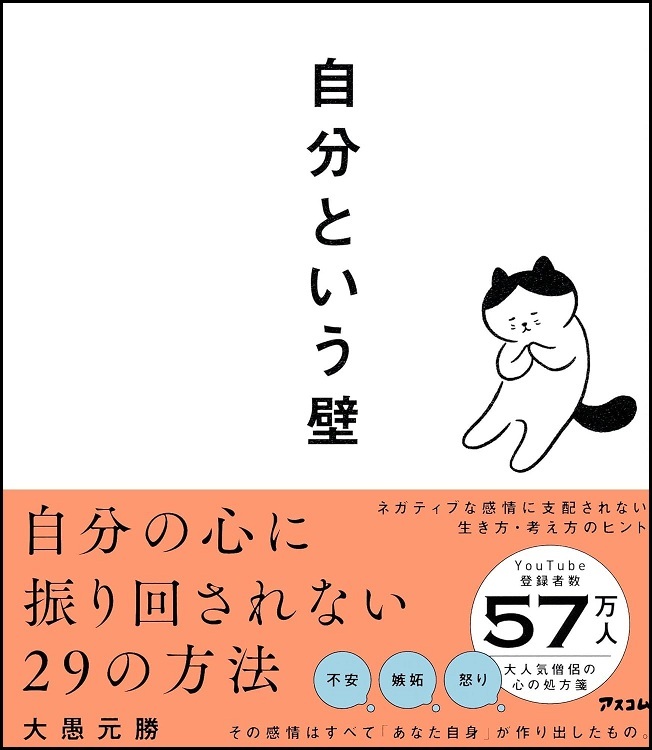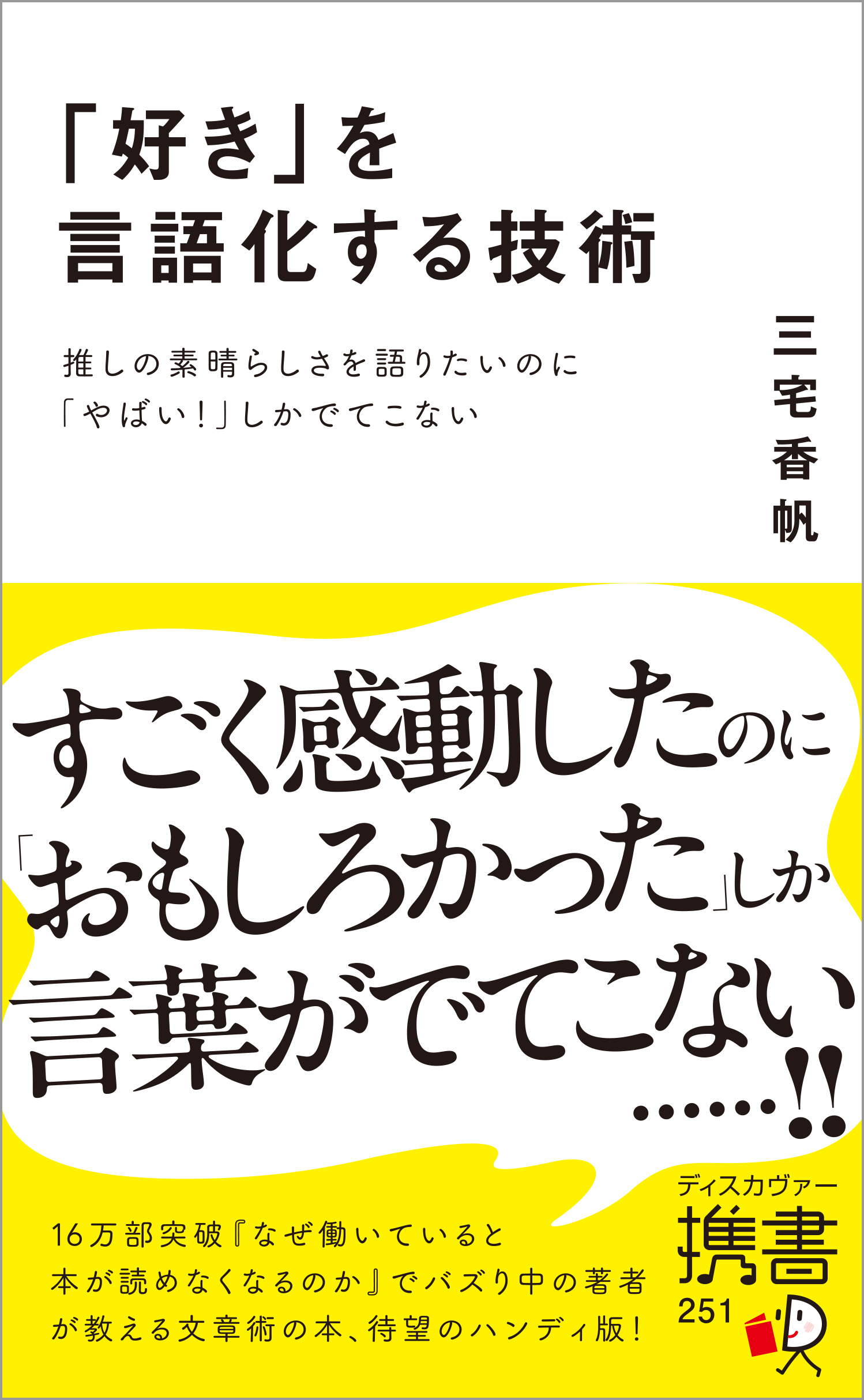転身
中央図書館 小原 文香
『セカンドキャリア 引退競走馬をめぐる旅』
片野 ゆか/著 集英社 2023年12月
この本では、引退競走馬たちの第二の「馬生」に光を当てる取り組みを紹介しています。年間約6千頭ものサラブレッドが引退する競馬界。その多くは食肉となる現実をご存じでしょうか。引退馬の余生は社会的な課題となっています。
食用となるはずだった馬を救うクラウドファンディング、癒しを与えるホースセラピー、たい肥を活用したマッシュルーム栽培など、さまざまな取り組みを取材しています。気性の荒いイメージがあるサラブレッドも、リトレーニングによって穏やかに人と触れ合い、新たな生を送ることができるそうです。動物ノンフィクション作家である著者が、犬や猫との比較を交えながら、アニマルウェルフェア(動物の福祉)の視点からも深く掘り下げます。
『自分という壁 自分の心に振り回されない29の方法』
大愚元勝/著 アスコム 2023年4月
多くの悩みに寄り添ってきた禅僧が、仏教の教えに基づき、苦しみから抜け出すヒントを示してくれます。「自分が嫌い」「いつも怒ってばかりで疲れる」「人間関係がストレス」といった悩みを抱えていませんか? 私たちは、自分や他人への思い込みや妄想から、過度な期待をしてしまい、それが苦しみのもとになっているといいます。他人は変えられなくとも、自分の考え方は変えられる。好き嫌いで割り切るのではなく、自分とは違うと受け入れることが大切だと説きます。
「諸行無常」という言葉は、すべての状況は常に変化し続けるという真理を示しています。喜びも苦しみも永遠に続くことはなく、その感情も自分の心が作り出すものであるため、コントロールできるというのです。古くから伝わる仏教の教えから、現代を生きる私たちも多くの学びを得ることができます。
『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』
三宅 香帆/著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2024年7月
文芸評論家であり、オタクでもある著者が、オタクでない人にも「推し」の素晴らしさを伝える「自分の言葉をつくる」技術を伝授します。発信媒体別の言葉や文章の作成法のアイデアに加え、聞き手と自分との情報量の差を埋めるプロセスなども紹介しています。読者の疑問に先回りして答える構成も心地よいです。
著者は本書で「言語化することの素晴らしさ」を体現していると感じました。好きなことを言語化することは、自己を見つめ、その物事を好きな自分を肯定することにも繋がるそうです。
私は数年前に「推し」と出会い、それまで全く縁のなかったジャンルに足を踏み入れました。本書を読み、すっかり感化され、あの頃の状況や気持ちをもっと書き留めておけばよかったと後悔しています。新たなスタートを切る人も多いこの季節、未来の自分のために、好きなことや今の志を言語化してみませんか。
よむとす
「よむとす」とは“読む“と“~せむとす”(ムトス)を合わせた造語です。
飯田市におけるムトスの精神を生かし、読むことにかかわる活動の推進と支援を目的とした読書活動推進の合言葉です。