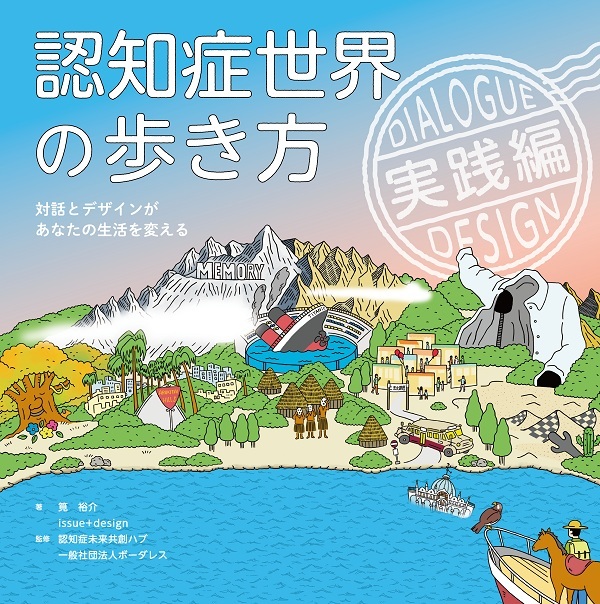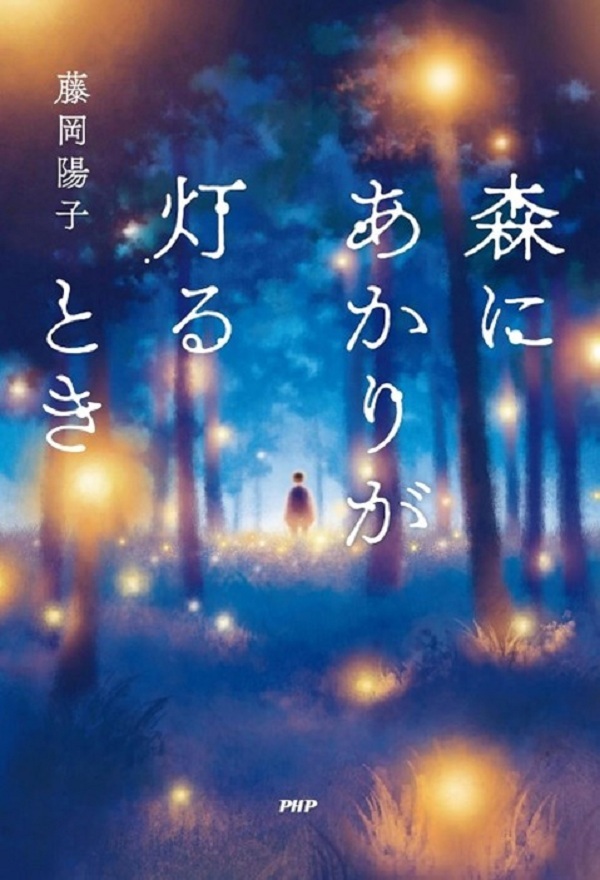それぞれの介護、それぞれの想い
中央図書館 伊坪 美穂子
超高齢社会の現代は、介護の問題に少なからず突き当たります。介護を受ける側と介護をする側のお互いの気持ちが噛み合わなかったり、どのように接したらよいのか迷ったりもします。子育てに正解が無いように、介護にも正解がありません。お互いの気持ちを尊重できる生活を送りたいものです。
『認知症世界の歩き方 実践編』
筧 裕介,issue+design/著 issue+design 2023年3月
認知症を患っている要介護者も大勢います。まったく他人ごとではありません。
この本では、認知症のご本人が生きる世界で見えているものや、思いやトラブルを、簡単なストーリーに仕立てています。そのなかのひとつ「ミステリーバス」では、認知症の世界を、「ここはどこ?」「どこから来たんだっけ?」と、行先の分からないバスに例えます。そして、トラブルの原因を、本人が直面した場面から推理し、その対処法を考えていきます。例えば“脳に記憶すべき情報” を見える化し、行先や経路を書いた資料を持ち歩く、という方法を紹介しています。後半では、家庭や身の回りの物のデザインについても書かれています。例えば、ご自分の部屋やトイレの入口は壁と色を変えて認識しやすくするなどの工夫をする。
症状は十人十色なので、偏見にとらわれない、否定から入るのではなくまずは「その通りだねー」と肯定的な言葉を発する。そして、何事もゆっくり、わかりやすく、生きづらさや寂しさを感じている本人を少しでも理解することが大事なようです。「対話」と「デザイン」によるヒントが満載です。
『森にあかりが灯るとき』
藤岡 陽子/著 PHP研究所 2024年10月
お笑い芸人になることを夢見ていた主人公の溝内星矢は、夢に挫折し、「森あかり」という名前の特別養護老人ホームで働くことになります。介護士、看護師、医師、施設長、そして利用者、それぞれの過去を背負った人たちが登場する小説です。
看護師の資格を持つ著者は、介護の現場に詳しく、施設介護の様子が小説の中でよくわかります。暗い森の中を歩く人たちの灯となるべく日々奮闘する人たちが、施設で起きる事件を通して、少しずつお互いのことを理解していきます。自宅で生涯を全うできれば理想ですが、家庭の事情などでそれが叶わない人もたくさんいます。だからこそ、介護をする人、介護をされる人の両方の生活を支えてくれる人たちが沢山いることを忘れず、その人たちに光が当たるように願わずにいられません。
最後に、脳を鍛えるための早口言葉をひとつ。『とっさに言葉が出てこない人のための脳に効く早口ことば』(別ウインドウで開く)(川島 隆太,大谷 健太/著 サンマーク出版 2024年08月)より
【 上海の3歳児 シャンさん 草食で小食 】
毎日声に出してしゃべると良いようです。
よむとす
「よむとす」とは“読む“と“~せむとす”(ムトス)を合わせた造語です。
飯田市におけるムトスの精神を生かし、読むことにかかわる活動の推進と支援を目的とした読書活動推進の合言葉です。