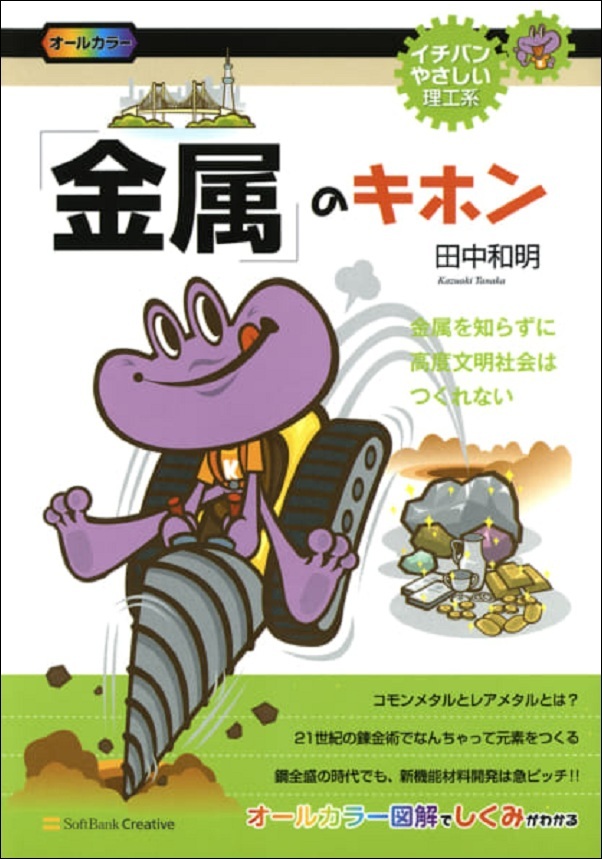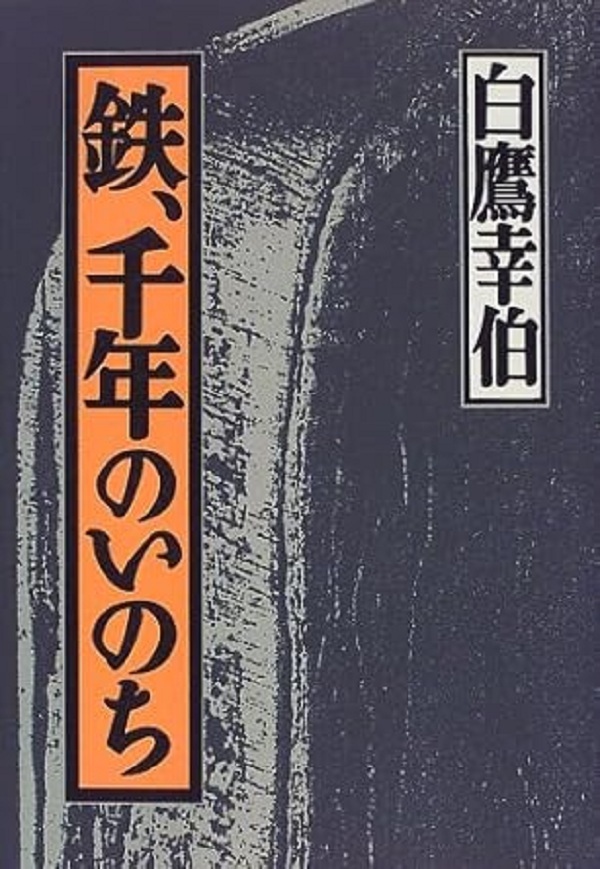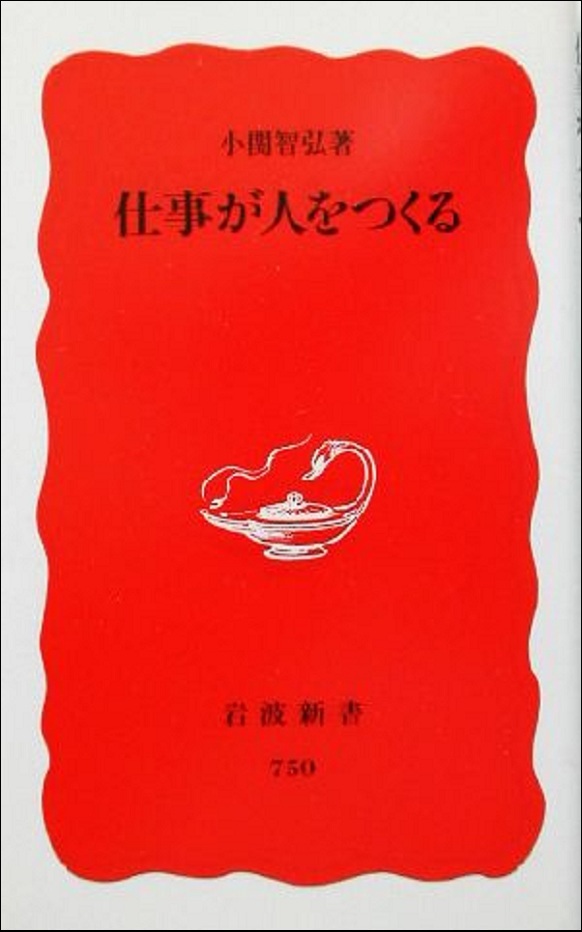「鉄」のあれこれ
中央図書館 小島 弘資
昨年、燕三条を訪ね、ステンレス食器の展示を見て美しさに息を飲みました。以前、八幡製鉄所の溶鉱炉を見学した時も胸が躍りました。鉄は、魅力あふれる素材のわりに、身近にありふれた存在のせいか関心を引くことが少ないように思います。世界史によれば、鉄器の登場が人類史の転換点となり、農具と武器の進歩が歴史に光と影を投げてきました。地球は、重量の3割以上を鉄が占める、「巨大な鉄の玉」だそうですが(後述『「金属」のキホン』)、もし鉄がなかったら人類の歴史はもっと穏やかなものだったかもしれません。今回は、この鉄にまつわる本を紹介します。
『「金属」のキホン』
田中 和明/著 ソフトバンククリエイティブ 2010年10月
少し古い本ですが金属の基本情報がわかる一冊です。生活に身近な携帯電話や貨幣に使われている金属から東京タワーの材料まで興味深い情報が紹介されています。また、地球の地磁気が、内部の鉄合金の回転によって生じ、宇宙からの有害な電磁波を防いでいること、ステンレスが錆びにくい理由と条件次第では錆びること、潜水艦から腕時計、医療器具まで、鉄に代わって使用されるチタン合金の実力など魅力あふれる話題が満載です。
『鉄、千年のいのち』
白鷹 幸伯/著 草思社 1997年6月
著者は、愛媛県松山市の生まれ。9歳から家業の鍛冶を仕込まれ、西岡常一棟梁との運命的な出会いにより「和釘」の鍛造に打ち込みます。西岡常一は、法隆寺の修復工事や薬師寺の金堂、西塔の復興などを手掛け、「最後の宮大工」と呼ばれた棟梁で、「千年の檜を使って千年もつ建物を建てる」が持論でした。薬師寺再建の際、著者は7,000本の和釘を西岡棟梁から注文されますが、当然、その釘も千年の歳月に耐えなくてはなりません。実際に、法隆寺の釘は1,300年間、国宝寺院を支えているそうです。
和釘とは、古代から日本の建築に使用されてきた、四角錐を細長く引き伸ばしたような形の釘で、現在の洋釘とは素材も形も全く異なります。鉄鉱石を原料に溶鉱炉で作られた鉄で大量生産される洋釘は、錆びやすく構造材を支えることが難しいのに対し、和釘は砂鉄を原料にたたら製法で作られた高純度の鉄を鍛造します。鍛造とは、日本刀と同様に鉄を叩いて鍛える製法で、強靭で切れ味鋭く、錆びにくい性質を持ちます。しかし、和釘の製造法は伝承されておらず、材料の調達も困難を極め、試行錯誤の連続でした。薬師寺金堂、西塔は、見えないところで著者の丹精込めた和釘が支えています。著者の和釘にかけた情熱と苦労、それを支え続けた西岡棟梁との交流が胸を熱くさせます。
『仕事が人をつくる』
小関 智弘/著 岩波書店 2001年9月
著者は、東京の工業高校卒業後、旋盤工一筋の職人で、50年以上にわたる町工場での体験をもとに作家活動をしています。旋盤とは、金属を高速で回転させ刃物で削る器械です。単純に見えて実は大変「奥行きの深い」仕事だそうで、熟練者は削る音や臭いで数字に現れない微妙な修正をします。そんなたたき上げの職人の目で、全国の「仕事師」を紹介したのが本書です。大企業ではなく地方の中小の町工場が舞台で、そこからF1車を製造する機械や宇宙用特殊カメラが作られます。世界中に数あるメーカーの中でその町工場でしか作れないものがあり、その陰には想像を絶する苦労や研究の積み重ねがあります。「ものづくり」の魅力を味わい深く伝えてくれます。
よむとす
「よむとす」とは“読む“と“~せむとす”(ムトス)を合わせた造語です。
飯田市におけるムトスの精神を生かし、読むことにかかわる活動の推進と支援を目的とした読書活動推進の合言葉です。