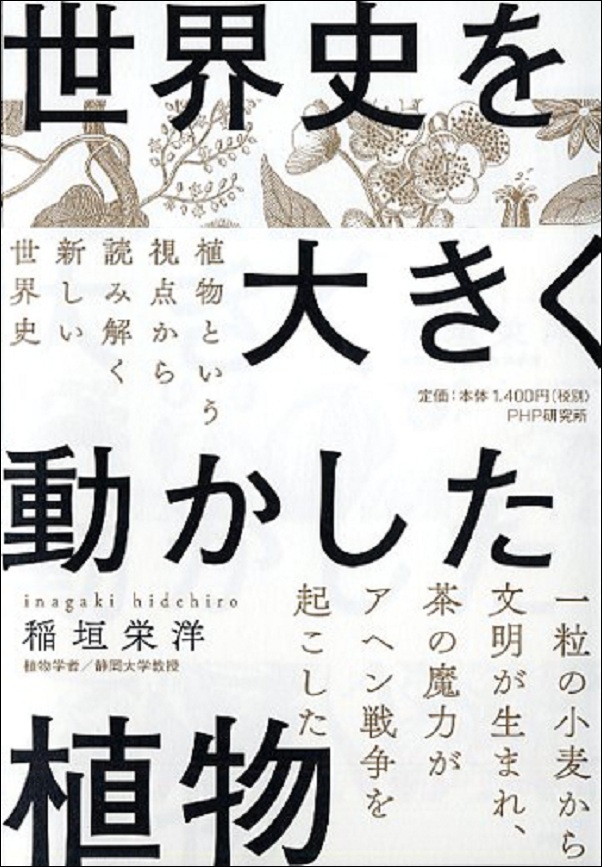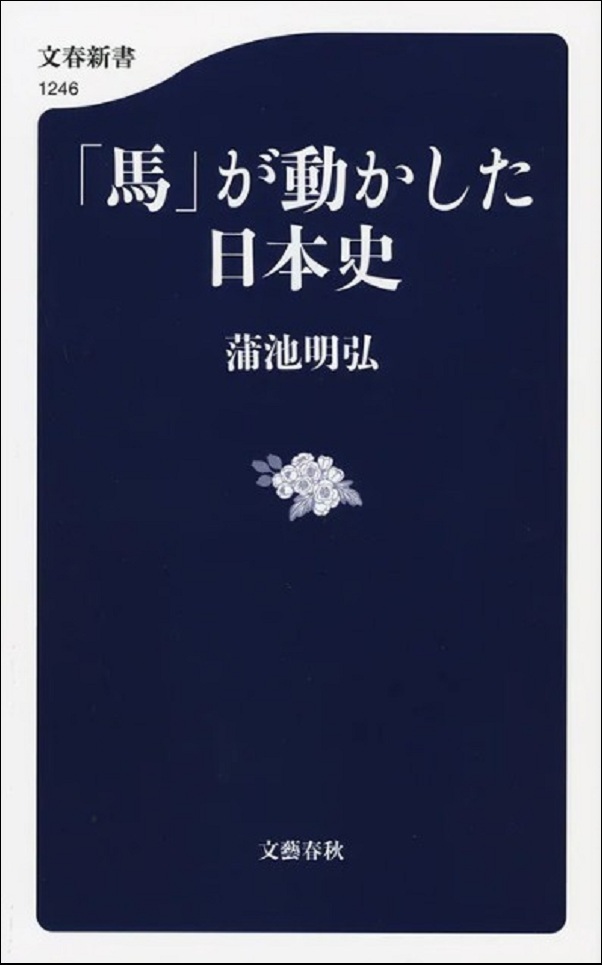生き物から見る人の歴史
中央図書館 牧野迪彦
なんとなく興味はあるけれど、どうやって触れたらよいのか分からない、そんな事柄が私にはいくつもあります。例えば歴史。あらましをざっと眺めてそこから楽しさを見出すのも難しい、さりとてディープな部分にいきなり踏み込むのも難しい、けれども触れるからには楽しみたい……。そんなわがままにも応えてくれるのですから、「本」というものは偉大です。
知らない事でも、元々興味のあることから切り込んだら楽しめるのではないか。今回私が紹介するのは、そんな思いつきから手に取って、楽しく歴史を学ぶことができた、生き物を視点に歴史を眺める本です。
『世界史を大きく動かした植物』
稲垣 栄洋/著 PHPエディターズ・グループ 2018年7月
それまで狩猟生活をおくっていた人類に農業を始めさせ、更に貯蔵ができ、人々の間で分けられることで人類に富の概念を気付かせたコムギやイネ。「大航海時代」「独立戦争」「アヘン戦争」「産業革命」といった、歴史の教科書でもおなじみの大きな出来事のきっかけとなったコショウ、チャ、ワタ……。植物のどんな性質が人々に求められ、あるいは魅了して人々の営みや歴史を動かしてきたのかが書かれた本です。人々が植物を求めるのは、飢えをしのぐためといった必要に駆られた時だけでは無いようです。チャに含まれるカフェインや、コショウやトウガラシに含まれる辛味成分といった、心身に作用し人に快楽をおぼえさせるもの、そんな身体の中でわずかな反応を起こすものが人を動かし、時に人々の運命を、時に国の形さえも変えてしまうということを知ると、植物がより魅力的にも、恐ろしいものにも思えてきます。読んでいると、人類が植物を利用して豊かになったというより、植物に突き動かされるようにして歩みを進めてきたようにすら感じてきます。
それから、今我々が当たり前のように食べている植物たちが、どんな紆余曲折を経て食卓に並ぶようになったのか、どんな魅力を持ったものなのかを知って、ちょっぴりお腹が減ってくる本でもあります。
『「馬」が動かした日本史』
蒲池 明弘/著 文藝春秋 2020年1月
みなさんは「日本史」というフレーズで何を思い浮かべるでしょうか。卑弥呼の肖像、華やかな平安貴族、近代の戦争……いくつも浮かぶイメージの中に、馬に跨る戦国武将、という情景が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。それだけ馬は日本史と馴染みのある存在ですが、元々日本列島には生息しておらず、古墳時代に朝鮮半島から持ち込まれて広がっていったのだそうです。
この本は、馬が日本に持ち込まれて以来、日本の歴史にどのような影響を与えてきたのか書かれた本です。速さと力強さを兼ね備えた馬の軍事的・経済的な影響力は、日本の勢力図を、時に隣国との関係をも動かしてしまうほどに大きかったのだ、ということを感じさせる本です。興味深いのは、さまざまな地域や勢力の興隆に、馬が育つのに適した土地柄が関わっているのではないかという、地理や土壌の知見をまじえた考察が多いことです。例えば、巨大古墳の造営地域や、平安時代の牧、有力な武士の活動拠点と、馬産地に適した火山性土壌(火山の活動によりできた、草原の環境が続きやすい場所)の広がりが重なっているという指摘です。山林のイメージが強い日本ですが、草原の国としての一面も持っていた、という部分には驚かされました。
よむとす
「よむとす」とは“読む“と“~せむとす”(ムトス)を合わせた造語です。
飯田市におけるムトスの精神を生かし、読むことにかかわる活動の推進と支援を目的とした読書活動推進の合言葉です。