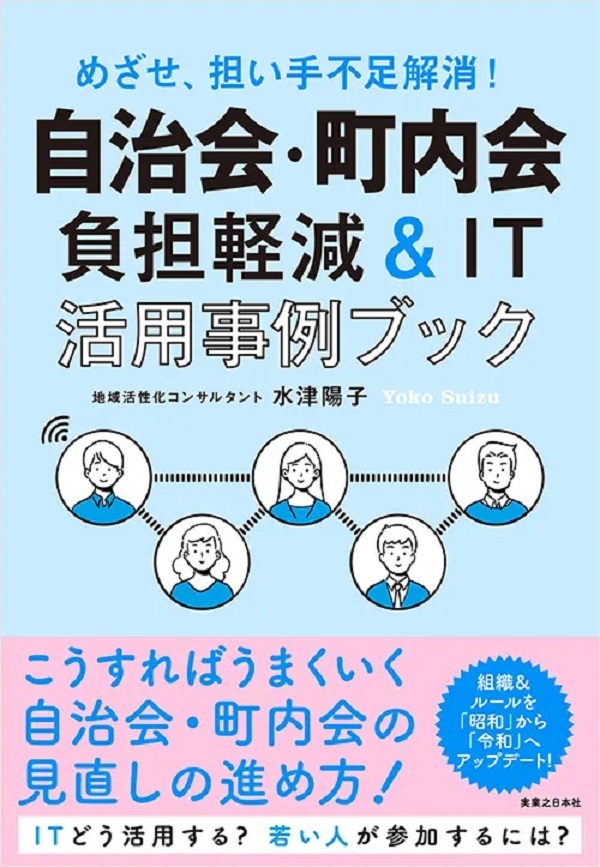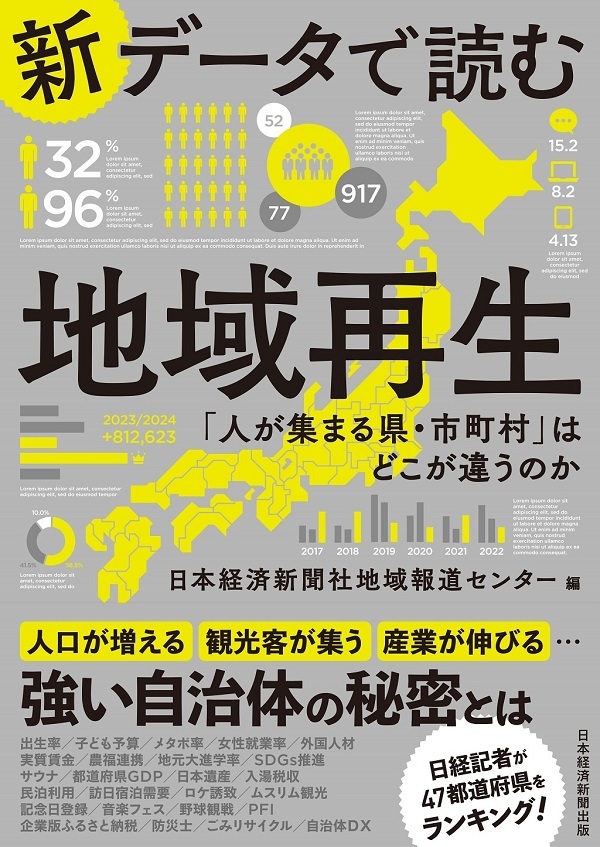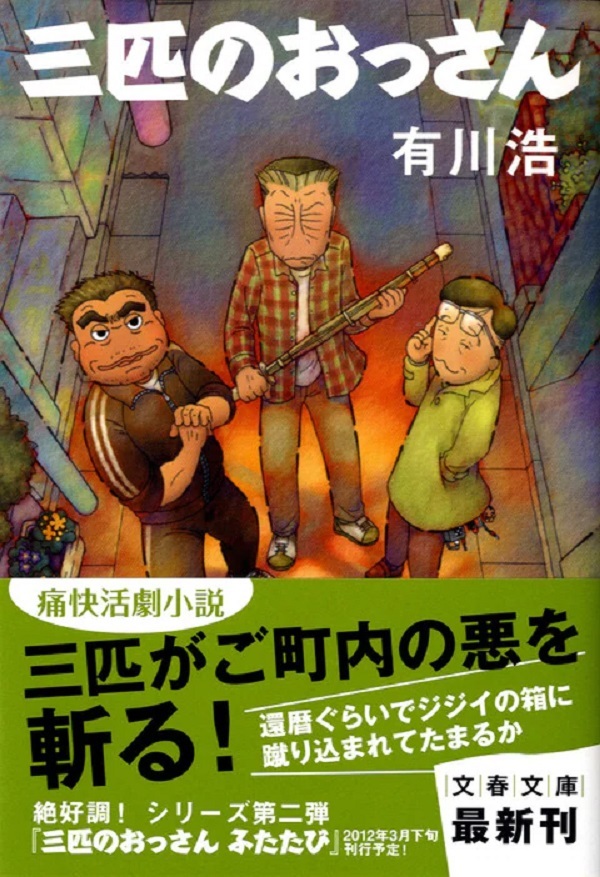地域貢献
中央図書館 唐木 知子
飯田市に住み始めて7年になります。この地に根を張って生活し地域に溶け込むことを目指し、今すぐできる地域貢献として、今年度は公民館の役員を拝命しました。
役員になり研修会に参加してわかったことは、わが地域の組合加入数は右肩下がりということ!今年度の組合加入率は46%、全体の半数以下だそうです。アフターコロナで地域の行事が再開されつつある中で、自治会の担い手不足、人集めも問題になっていることがわかりました。そして、どうやらそれは我が地区ばかりの問題ではなく、全国的にみられる傾向のようです。本を通して自治会や公民館活動のあり方を一緒に考えてみませんか?
『自治会・町内会負担軽減&IT活用事例ブック めざせ、担い手不足解消!』
水津 陽子/著 実業之日本社 2022年6月
こちらの本は、あらゆる自治会の問題をどう解消したらいいかの実例を紹介しています。役の負担を軽減する提案、組織やルールを令和の時代に合うようにアップデートさせる提案も紹介されています。例えば、若い世代へ地域のイベントを周知するためにLINEやInstagramなどのSNSを活用すること、担い手不足の自治会を統合させること、マンションの自治会の運営案などがあります。これらは、どの地域でも課題となっている点ではないでしょうか。そして、その課題を解消させるために果敢に問題に立ち向かっている仲間が全国にいることが何より励みになり、我が地区も取り入れてみようか!?と励まされる1冊です。
『新データで読む地域再生 「人が集まる県・市町村」はどこが違うのか』
日本経済新聞社地域報道センター/編 日経BP日本経済新聞出版 2024年4月
データサイエンス、という言葉が聞かれるようになりました。データサイエンスとは、大量のデータから情報、法則などを読み解くこと、またはその情報処理の手法に関する研究を行うことです。この本は、まさにこのデータサイエンスの考え方に基づき、「急激な人口減少をはじめとする地域課題に向き合い解決策を考えるためにはデータ(数値情報)からまずリアルな姿をできるだけ正確に読み解き、伝える必要がある」との問題意識から作られたものです。例として、地方都市であっても、出生率が高まっている町の様子を覗くと、大きな企業を誘致して雇用を確保していたり、共働きしやすい環境を整備したり、国際的な特色ある教育環境を整備したりという背景があることがわかりました。先進事例を学ぶことで、地域活性化のヒントが見つかるかも知れません。
『三匹のおっさん』
有川 浩/著 文藝春秋 2009年3月
人気作家が描いた還暦を迎えたおっさん3人が主人公の物語。この主人公の3人は個性が際立っていて、年齢を感じさせない、いや、それどころか若者よりパワフルな活躍で地域や家族に起きる問題を解決していきます。私が公民館活動を通して出会う皆さんは、こちらの登場人物のように溌溂とした方ばかりです。一緒に活動することで、地域の歴史を学べたり、私のような世代も性別も違う者の意見にも耳を傾けてくださったりと、尊敬することが多くあります。お話しすると元気が出て、いつもこの本を思い出します。世代を超えて楽しめる物語ですので、ぜひたくさんの方に読んでいただき、それぞれの感想を聞かせほしいと思います。
十数年前にドイツのシュバルツバルトを訪れたことがあります。かつて酸性雨で枯れた「黒い森」と言われた地域ですが、私が訪れた時には生物多様性に配慮された植林活動のもと、持続可能な環境整備がなされた地域に生まれ変わっていました。また、住民が出資して、風力発電の風車を建設した地域もありました。そこで感じたのは、自分たちの地域は自分たちの手で作っていくという強い主体性です。私たちの自治会や公民館活動も同じではないでしょうか。誰かが決めてくれるのを待つのではなく、住民一人一人が主役になって自分たちの地域のことを10年先100年先まで見据えて一緒に考えていく。私も一住民として、自治会活動という伝統のバトンを受け取り、時代に合わせて形を変えながら次の世代に渡していきたいと思います。この活動が「できればやりたくない面倒なこと」から「ぜひやってみたい面白いこと」に変わるように、楽しんで活動することが私にできる地域貢献だと思っています。
よむとす
「よむとす」とは“読む“と“~せむとす”(ムトス)を合わせた造語です。
飯田市におけるムトスの精神を生かし、読むことにかかわる活動の推進と支援を目的とした読書活動推進の合言葉です。