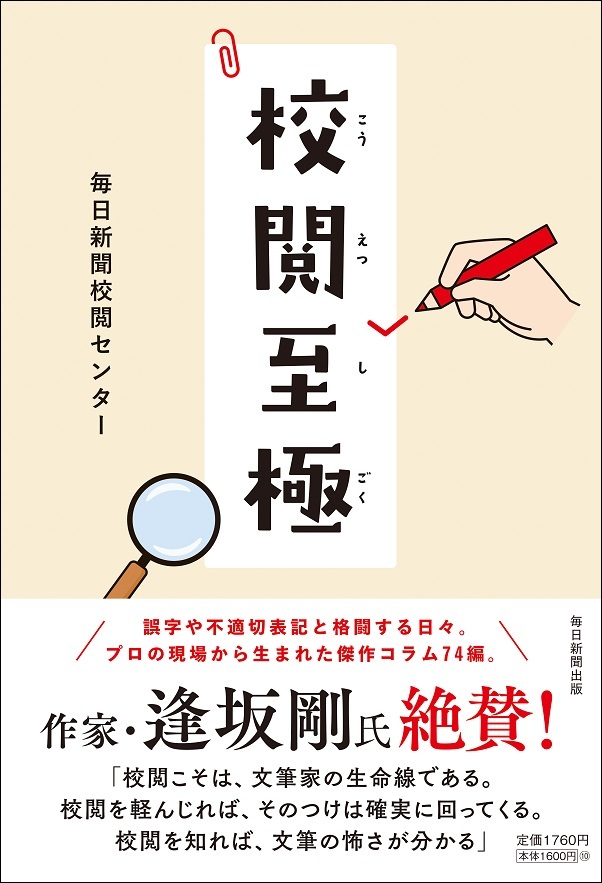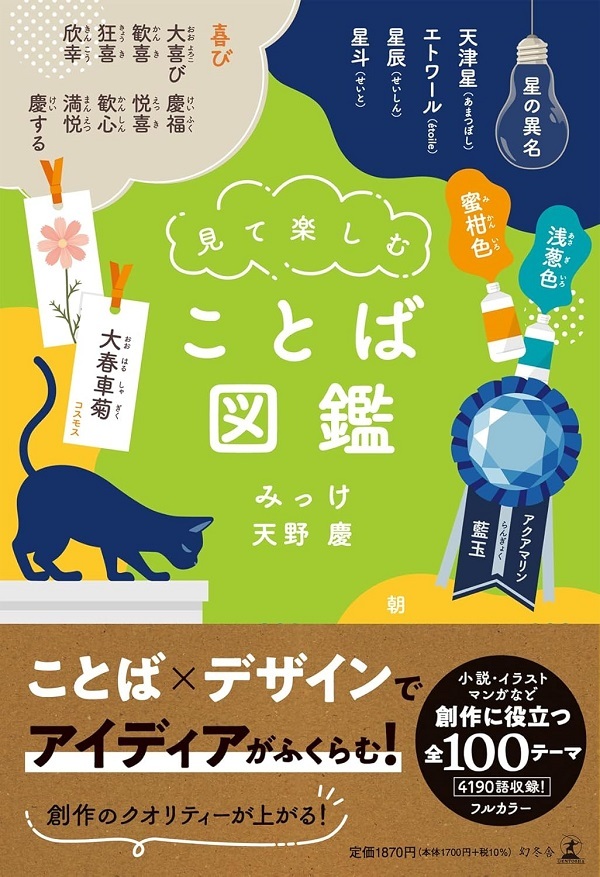「ことば」
中央図書館 寺沢 しのぶ
小学校2年生の息子は毎日算数と国語の宿題があります。その答え合わせは各家庭ですることになっていて、私が小学生だったころとは計算の仕方や考え方が違っていたりして、これがなかなか大変です。それでも、なんとか親の威厳は保たれていますが、先日学校から宿題が返却され息子に「答え合わせが間違っていたよ」と言われました。「えっ?」見てみると国語のプリントでした。国語は算数より自信あったのに…。間違っていたところは「通り」という漢字のふりがなを「とうり」と書いてありました。「あっ!」すぐに「とおり」の間違いだと気づきました。
私が、普段何気なく使っている「ことば」にも思い込みや勘違いがあるかもしれないと、あらためてその難しさを感じました。そんな「ことば」について書かれた本をご紹介します。
『校閲至極』
毎日新聞校閲センター/著 毎日新聞出版 2023年8月
この本は毎日新聞校閲センターの記者たちが『サンデー毎日』に持ち回りで連載していたコラムをまとめたものです。
校閲記者といえば、新聞などの記事に誤りがないか精査するいわば「ことば」のプロです。私のような素人の間違いとはレベルが違う難しい内容かと思いきや、とても読みやすく面白くてアッという間に読んでしまいました。意外にも私レベルの間違いがありました!「オホークツ海上にある発達した低気圧」「コンビ二エンスストア」--お気づきですか「オホーツク」でなく「オホークツ」に、「コンビ二エンスストア」の「ニ」が漢数字の「二」になっています。また、夏に白熱する全国高等学校野球選手権大会ですが、この時期に「三つの気をつけたい言葉」として「檄を飛ばす」「喝を入れる」「吹奏学部」が挙げられています。どれも紙面を賑わせそうな言葉ですが、その説明はとても納得するものでした。このほかにも日常的に誤解して使っていることばや間違った表現を、今まで無意識に使ってきた自分を猛省しました。
誤植を見つける以外にも「校閲」では事実確認も行います。例えば「銀座線 虎ノ門駅」・「日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅」などの「虎ノ門」の表記に対し、固有名詞である「虎の門病院」の「の」はひらがなという確認。霞が関と霞ヶ関、丸の内と丸ノ内などの表記にも注意が必要とあります。さらに、差別表現や記事を読んで不快に感じないか、表現は適正か、記事によって先入観を与えないかなど「校閲」の仕事は多岐にわたります。
新聞記事ひとつひとつがこうした幾重もの校閲を経ることで、私たちに正確な情報が届くことをこの本で知ることができました。
『見て楽しむことば図鑑』
みっけ/著 天野 慶/著 幻冬舎 2023年11月
歌人でもある著者は、短歌を詠みはじめた18歳のころ、ピカソの「青の時代」という作品の〈まだ若く貧しく、青い絵の具しか買えなかったため、青で描かれたともいわれている〉という解説を見て、「絵の具はたくさんの色を使うのにはお金がかかるけれど、歌を詠む時の「ことば」は、どんな高貴で貴重なものでも、なんて自由に使うことができるのだろう」と感動したそうです。
この本はその感動をもとに、100のテーマで「ことば」を集めて作られたものです。例えば、「光のことば」というページには、夜の街灯の薄暗い光の下に「明かり、煌めく、煌々、光明…」などの光に関することばが浮かびあがるデザインになっています。このほかに「海のことば」「猫のことば」「悲しみのことば」「恋と愛のことば」「旅のことば」など、ひとつひとつのテーマをイメージしたイラスト、フォントにまでこだわった素敵なデザインになっています。眺めるだけでも十分楽しめますが、そこにある「ことば」を使って何か表現してみたくなるようなそんな本です。
ぜひ、お手にとって眺めてみてください。
よむとす
「よむとす」とは“読む“と“~せむとす”(ムトス)を合わせた造語です。
飯田市におけるムトスの精神を生かし、読むことにかかわる活動の推進と支援を目的とした読書活動推進の合言葉です。