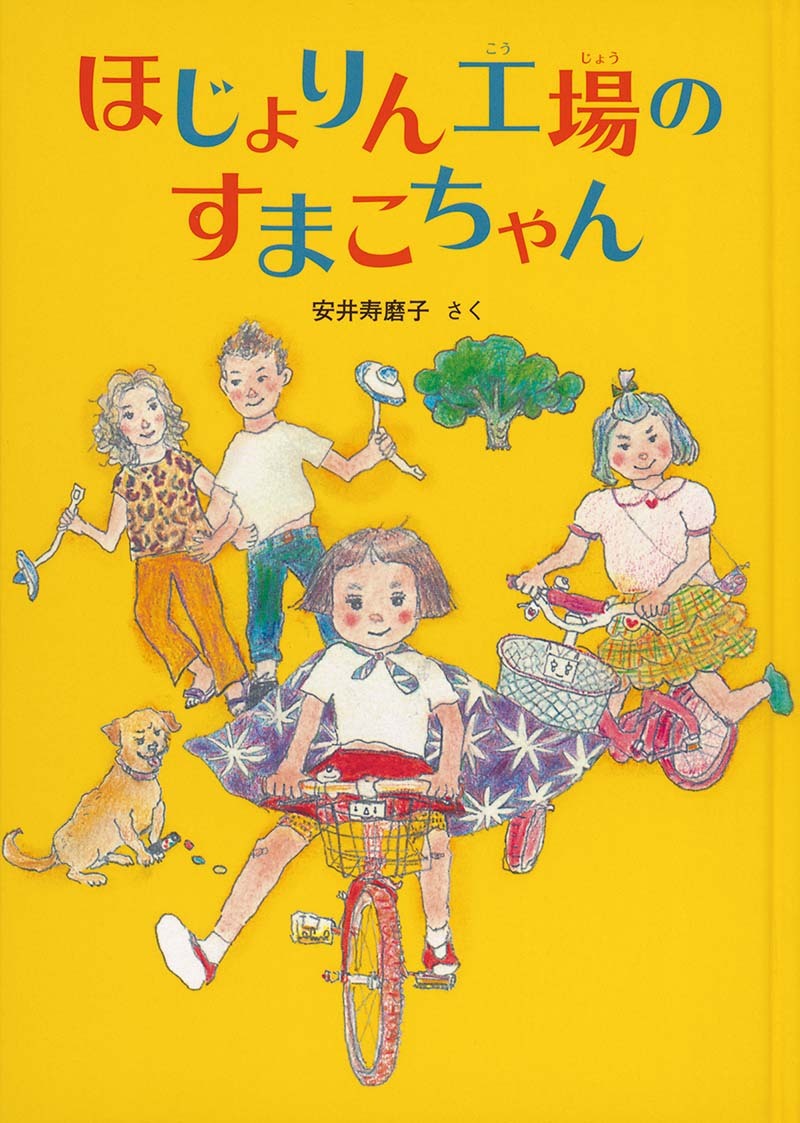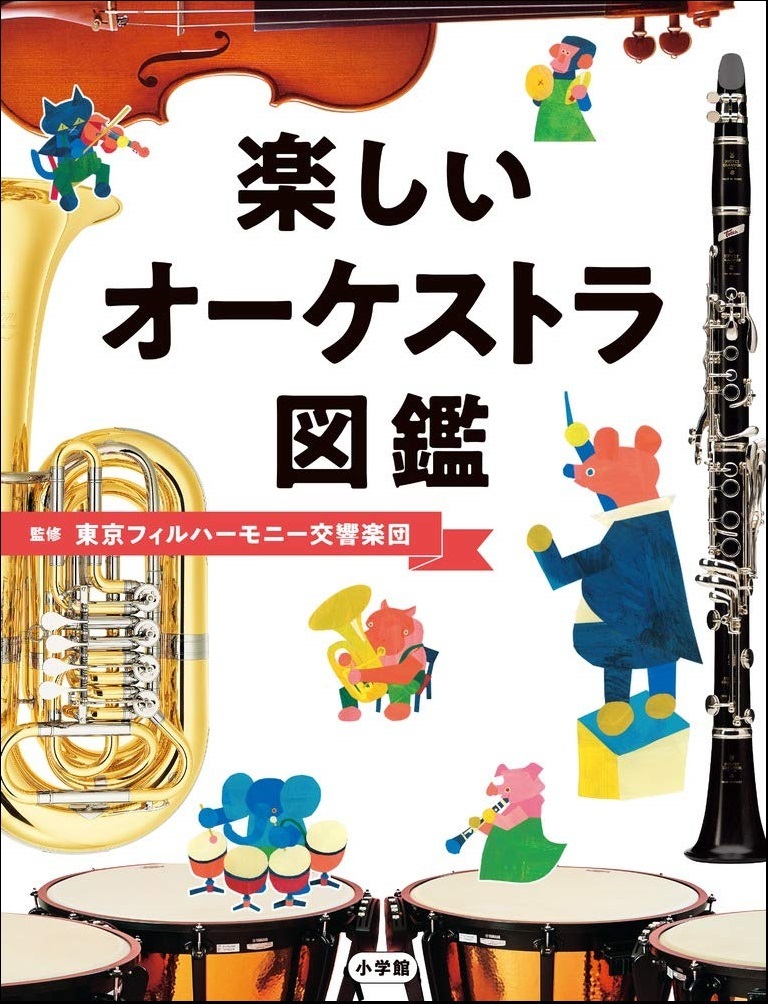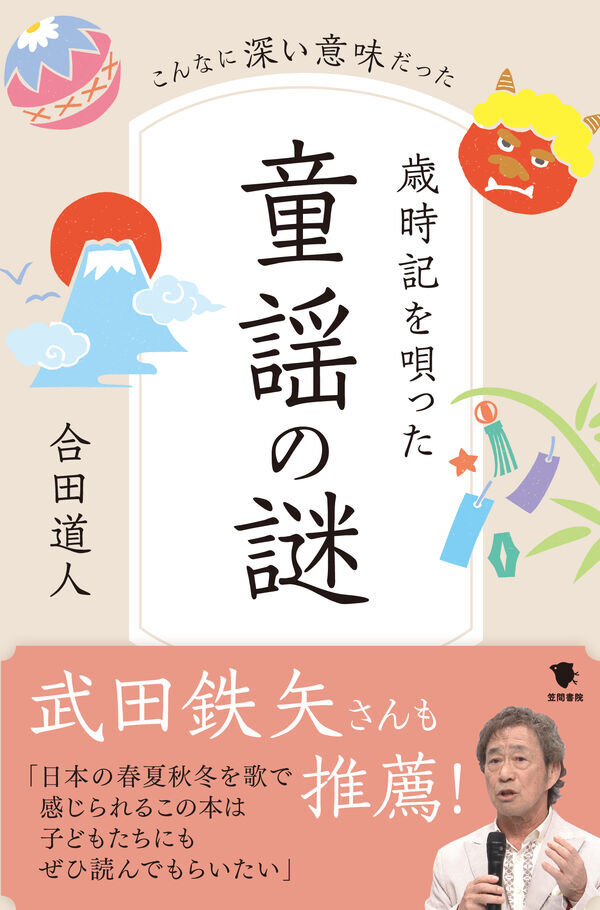はーるかぶりに
中央図書館 森山 ゆり
今年私が、はーるかぶり(飯田弁で「久しぶり」)に体験したことをテーマに3冊の本を紹介します。
『ほじょりん工場のすまこちゃん』
安井 寿磨子/さく 福音館書店 2022年2月
何十年ぶりかに自転車に乗りました。風を切って走るのがとても気持ちよく、なんだかわくわくして子供の頃を思い出しました。紹介する本の主人公すまこは、のんびり屋の小学生。すまこは「のんびりふらふらガーラガラ」と今日もころころ(補助輪)つきの赤い自転車で家のまわりを行ったり来たり。すまこの家は子供用自転車の補助輪工場なので、友達に「おとうちゃんがころころ作ってるから、まだころころつけてるん?」とからかわれても「ええねん、こけへんし。」と気にしません。
ところがある日、おとうちゃんが「補助輪はずすぞ!」と言い出します。そして絶対無理だと思いながら練習がスタートします。補助輪なしで自転車に乗れた時の空想をするすまこや、先生や大人になにか聞かれると、いろいろ考えすぎて最終的になにも言葉が出てこないすまこが、なんとなく小さい頃の自分と重なり応援したくなりました。おとうちゃんに「勇気や!もっと勇気を出せ!」と言われますが、勇気なんて言葉はすまこの頭の中にはありません。結局補助輪が取れないまま新学期が始まってしまいますが、あることをきっかけにすまこは勇気を出して頑張るようになります。
昭和40年代の大阪を舞台にしたクスッと笑えてちょっとしんみり、人情味あふれる、著者安井寿磨子さんの自伝でもあります。
『楽しいオーケストラ図鑑』
東京フィルハーモニー交響楽団/監修 小学館 2018年10月
何十年ぶりかにオーケストラの生演奏を聴きました。吹奏楽部の息子に誘われて5月に開催された「オーケストラと友に音楽祭」に行ったのです。「オーケストラは何人で構成されているのか?」、「楽器は何種類あるのか?」、素人の私は疑問が沢山浮かび、気になって手にとった本です。ページをめくるとまず、「オーケストラって何?」という疑問に答えてくれます。そして「オーケストラの一日」を時間を追って見ていくことができます。演奏者は同じ時間に来て練習していると思いきや、管楽器の演奏者は特に早く会場に来て練習しているのだそう。なぜかというと、管楽器は温度で音が大きく変わるため事前に楽器を温めてよい状態にしておくのだそうです。「温めるってどうやって…?」息子が「息を入れて(吹いて)温めておくんだよ。」と教えてくれました。なるほど、そういうことか!
私が一番興味深く読んだのは、オーケストラの主な楽器が東京フィルハーモニー交響楽団のそれぞれの奏者とともに、ひとつひとつ丁寧に紹介されているところです。そして演奏会を聴く観客のマナーも、オーケストラと一緒にその日の公演をつくっているのだということがわかります。かわいらしい動物たちのイラストとともに見ても読んでも楽しめます。
『歳時記を唄った童謡の謎』
合田 道人/著 笠間書院 2024年1月
何十年ぶりかに、私が保育園児だった時の担任の先生に出会いました!明るく優しく、おひさまのような、大好きだった先生。そんな先生と一緒に歌を歌うことが好きだった記憶がふっと蘇ってきました。紹介する本には、自分も含めきっと誰もが幼いころから春夏秋冬の中でよく口ずさんできた童謡が載っており、その歌詞に込められた意味や想い、曲が作られた背景などがわかりやすく解説されています。
夏になるとつい口ずさむ「ウミハヒロイナ オオキイナ…」で始まる「海」という歌。昭和16年に「海」の歌が文部省発行の『ウタノホン 上』に「ウミ」のカタカナ表記で掲載されました。この頃の子供たちの夢は戦争に勝つこと、兵隊になることだったそう。私がこの歌を歌いながら想像していた景色とは全く違う景色や想いを抱えて当時の子供たちは歌っていたのだということがわかり、なんともいえない気持ちになりました。「この歌の裏に隠された本当の意味など、身を持って知らなくていい。いや、知ってはいけないのだ。だからこそ、知っておく必要があるのだ」という著者の一文が大きく印象に残りました。今年も「海」を口ずさむ夏がやってきました。
よむとす
「よむとす」とは“読む“と“~せむとす”(ムトス)を合わせた造語です。
飯田市におけるムトスの精神を生かし、読むことにかかわる活動の推進と支援を目的とした読書活動推進の合言葉です。